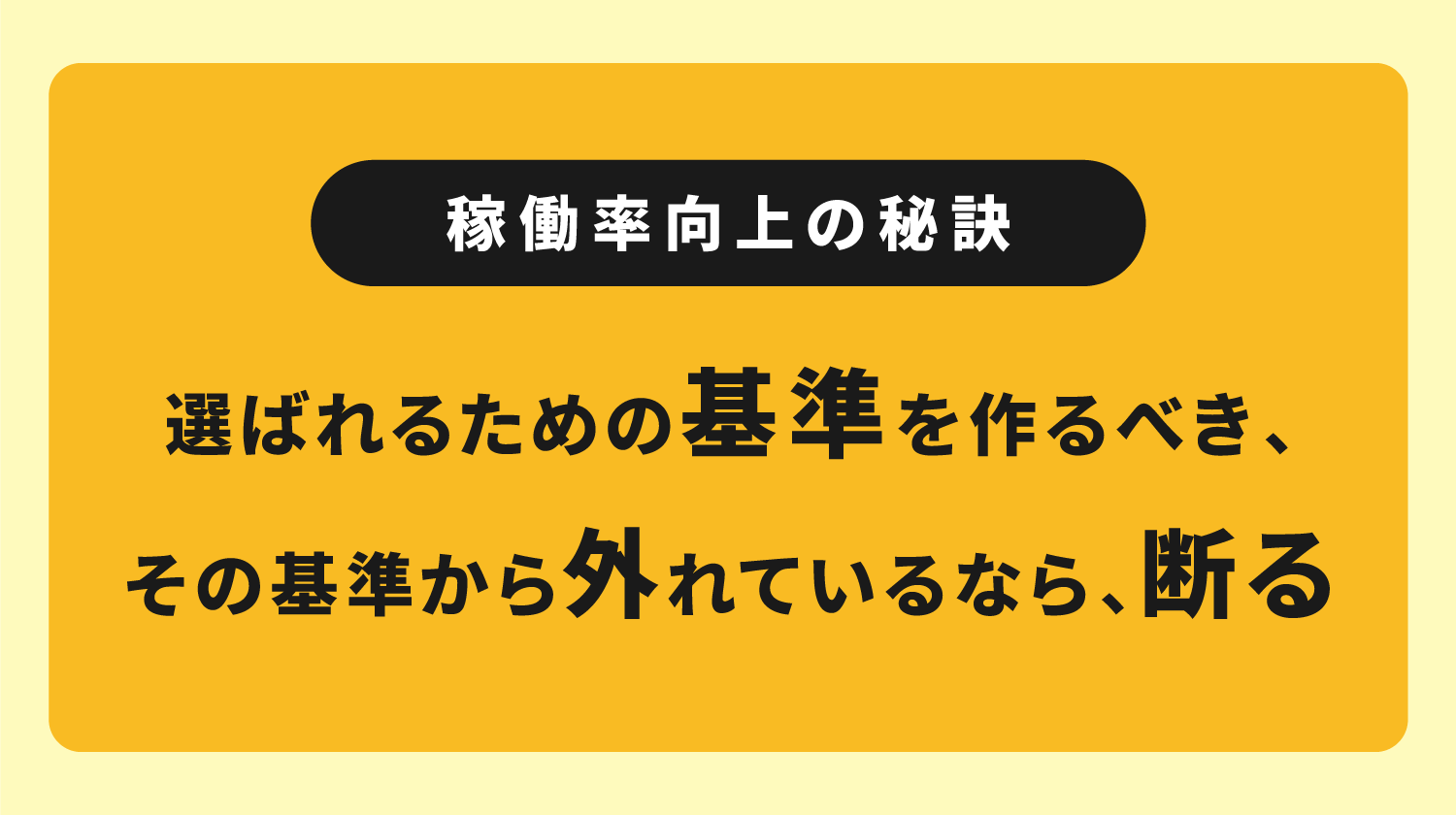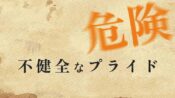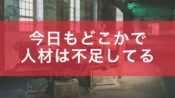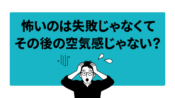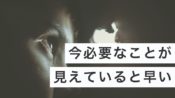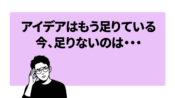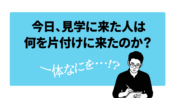「何でもやります」はNG。稼働率を上げたデイサービスに共通することとは?
僕のブログサイトを通じて、「デイサービスの稼働率について相談したい」とご連絡をいただくことがあります。
その際にまず、現状がどうなっているのかを相談者の方にヒアリングするのですが、必ずと言っていいほど出てくる質問があります。
藤見さんがコンサルしているデイサービスで……
「稼働率を上げることに成功したデイサービスって、どんなことをやってるんですか?」
この質問をしたくなる気持ち、すごくわかります。
「自分たちには思いつかない何か特別な方法を、他のデイサービスはやっているんじゃないか。きっとそうだ。」
そう思いますよね。
だから、
「その方法さえ知ることができれば、自分たちも稼働率が上げられるはず。」
──そう、考えていませんか?
そう問い返すと、
皆さん素直に「…はい」と頷きます。
その時、僕が必ずお話するのは、
「新しいことをプラスする前に、まず気を付けている“ある視点”があります」
という話です。
それが、
「何を“やらない”と決めているのか?」
という視点です。
ところで、
あなた(相談者さん)のデイサービスでは「これはやりません、できません」と、はっきり決めていることがありますか?
「どんな方でも受け入れます」
「どんな要望にも応えます」
「新規なら誰でも大歓迎です」
そんなスタンスで運営していませんか?
入院や体調不良で利用が停止になったり、中断したり、気付けば稼働率がじわじわと低下して、赤字スレスレの経営に追い込まれていく。
そんな状況になると、つい「誰でも来てください」と言いたくなる気持ちは、痛いほどよくわかります。
同時に、
介護の仕事には“誰かのために頑張りたい”という優しさが根底にあります。だから、「お断りする」「線引きする」といった発想に、ちょっと抵抗を感じる人も多いかもしれません。
でも皮肉なことに、
あなたが今一番知りたい「稼働率を上げることに成功したデイサービスの共通点」は、まさにその逆の考え方にあります。
その共通点は、「何をやらないかを必ず決めている」ということです。
以前、とある県で複数のデイサービスを経営している法人から相談を受けました。
「スタッフは頑張っているんですが、なかなか利用者数が伸びなくて…」と。
経営者さんの言葉通り、スタッフさんは仕事熱心で、利用者さんへの対応も丁寧で、どこにも手を抜いていません。
現場ができる努力は、すでに十分やっている。
それでも、稼働率は年々下降し、6割の壁を越えられない。
ヒアリングの後、実際に現地を訪問してみました。
そして、実際のデイサービスの運営状況について、現場でスタッフさんから詳しくお話を伺いました。
すると、「ああ、なるほどな」と、あることに気づきました。
このデイサービスには「選ぶ」という選択肢が存在していない
外部からの依頼やケアマネさんからの要望に対して、まるで下請け会社のように、すべて「はい」と受け入れてしまっている。
自分たちを苦しめるような依頼にも、後先考えずに対応しようとしている。
何でも請け負いすぎてしまっている。
そんな運営をしている。
そのスタンスこそが、このデイサービスが選ばれにくい(つまり稼働率が上がらない)原因だと気付かずに、必死に努力を続けている。
スタッフさんとの話を終えた後、
経営者の方に、こう問いかけました。
「いま一度、このデイサービスは“誰に来てほしい場所”なのかを決めてみませんか?そして、勇気を出して、“合わない方”もあえて定義してみませんか?」
最初は、経営者さんもスタッフさんたちも戸惑いがあるように見えました。
「選んでもらいたいのに、せっかく声を掛けてもらったところを、あえてお断りするなんて…逆効果になりませんか?」と。
その気持はすごくわかる。
でも、「どんな方でもOKです」という曖昧な立ち位置のまま地域のケアマネさんに紹介をお願いしても(集客活動を続けたとしても)、必然的に自分たちの不得意なケースまでどんどん増えていってしまいます。
不得意なケースを無理して受け入れたことで、目先の売上(稼働率)は潤うかもしれませんが、現場の負担は増すばかり。
その対応に追われているうちに、今まで守ってきたサービスの質が保てなくなります。
そして結局、既存利用者さんの満足度が下がってしまう。
そして何より深刻なのは、疲弊感が蓄積されて、営業や集客に対する現場のモチベーションが下がっていくこと。
こうしたリスクを抱えることになります。
そこで、このデイサービスでは、経営者さんと主要スタッフを交えた全体ミーティングを何度か重ねて、「コンセプトの再定義」に取り組むことになりました。
大切なのは、
「選ばれるためには、私たちも選ぶ側になる必要がある」
という視点です。
この考え方にピンと来ない方、あるいは少し怖く感じるという人は、次のように考えてみるのもひとつの方法です。
それは、
最終的に、自分たちが「何で選ばれたいのか?」が明確になっていなければ、利用者やケアマネジャー側も、「何を基準にあなたを選べばいいのか」がわからない。
だからこそ、自分たちが選ばれるための“基準”を作るべきだし、その基準に合わない依頼は、勇気を持って断るべき。
「私たちの得意分野はコレです」
「この困りごとは、私たちが一番力になれると思います」
そうやって地域に対して自分たちをアピールする。
裏を返せば、
「申し訳ないけれど、その他の困りごとは得意ではないので、別のデイサービスの方がきっと力になれると思います」
と、言っているのと同じこと。
それは決して、上から目線な態度ではなく、大名商売してるわけでもありません。
むしろ、誠実で正直なスタンスだと僕は思います。
──結果、
このデイサービスがコンセプトを再定義(明確に)したことで、スタッフさんたちの「迷い」がなくなり、行動に一貫性が生まれました。
そして、集客活動にも勢いが出てきました。
それまでは、利用者さんの顔色を伺いながら、毎回手探りで「どうすれば相手に気に入ってもらえるか」を模索していた状態でした。
でも今では、
「私たちが得意としているのは、こういうサービスです。だから、それを求めている方に来ていただけると嬉しいです」
「合わない方、そうじゃない方は、申し訳いないですが別の場所をご案内します。ごめんなさい」
と、明確に表現できるようになっています。
これで特に大きく変わったのは、外部からの“紹介の質と数”です。
「この方は運動意欲が高いから、ぴったりだと思う」
「午前中だけの希望があるから、合うと思って」
といった具合に、ケアマネさんたちも迷わず紹介してくれるようになりました。
紹介の精度が上がれば、契約後のミスマッチも減ります。
すると、必然的に現場のオペレーションの混乱も少なくなります。
この好循環が、デイサービスの活気と集客力を支えてくれるようになるわけです。
僕は思います。
「やらないことを決める」という視点は、今後のデイサービス経営において、とても重要な柱になるはずです。
何億円も潤沢な資金があって、スタッフが無限に採用できて、依頼された理想のケアを何でも実現できる。ぜんぶ叶えてあげられる。
そんなことが可能な会社(デイサービス、介護施設)があるなら、この話は聞き流してくれて大丈夫です。
でも、そんな会社は、おそらく存在しない。
であるならば、なおのこと、
限られたリソース(ヒト・モノ・カネ)を「すべての人」に合わせようとするのではなく、「しっかり満足してもらえる誰か」のために使うべきだと思います。
「どんな方でも受け入れます」
「どんな要望にも応えます」
「誰でもいいから来てください」
この姿勢は、一見やさしく思えるかもしれませんが、実は誰にもその声が響かない、という大きなリスクを抱えているのです。
「やらないことを決める」というのは、冷たいことでも、逃げることでもありません。
むしろ、
「これに全力で取り組みます」と胸を張る強さであり、
「自分たちの価値を信じている」という決意の表れです。
頑張っているのに、結果が出ない。
スタッフは必死なのに、利用者が増えない。
──もし、そんな状況に心当たりがあるなら、一度立ち止まってみてください。
選ばれるデイサービスに必要なのは、
「すべてを提供すること」ではなく「自分たちの価値」を、きちんと届ける覚悟を持つことです。
「自分たちは、何を“やらない”と決めているだろうか?」
この問いに向き合うことが、次の扉を開く鍵になると僕は思います。
それでは、また!
藤見メルマガ
特典のお知らせ

「デイサービス集客のヒントが見つかる!」と話題の”介護集客セミナー動画(90分)”をプレゼント!さらに、完全書き下ろしの”集客レポート(14,000文字)”も無料配布中です。デイサービスや介護施設の集客力アップに役立つヒントが盛りだくさんの内容です。ぜひこの機会にセミナー動画&レポートをGETしてください。