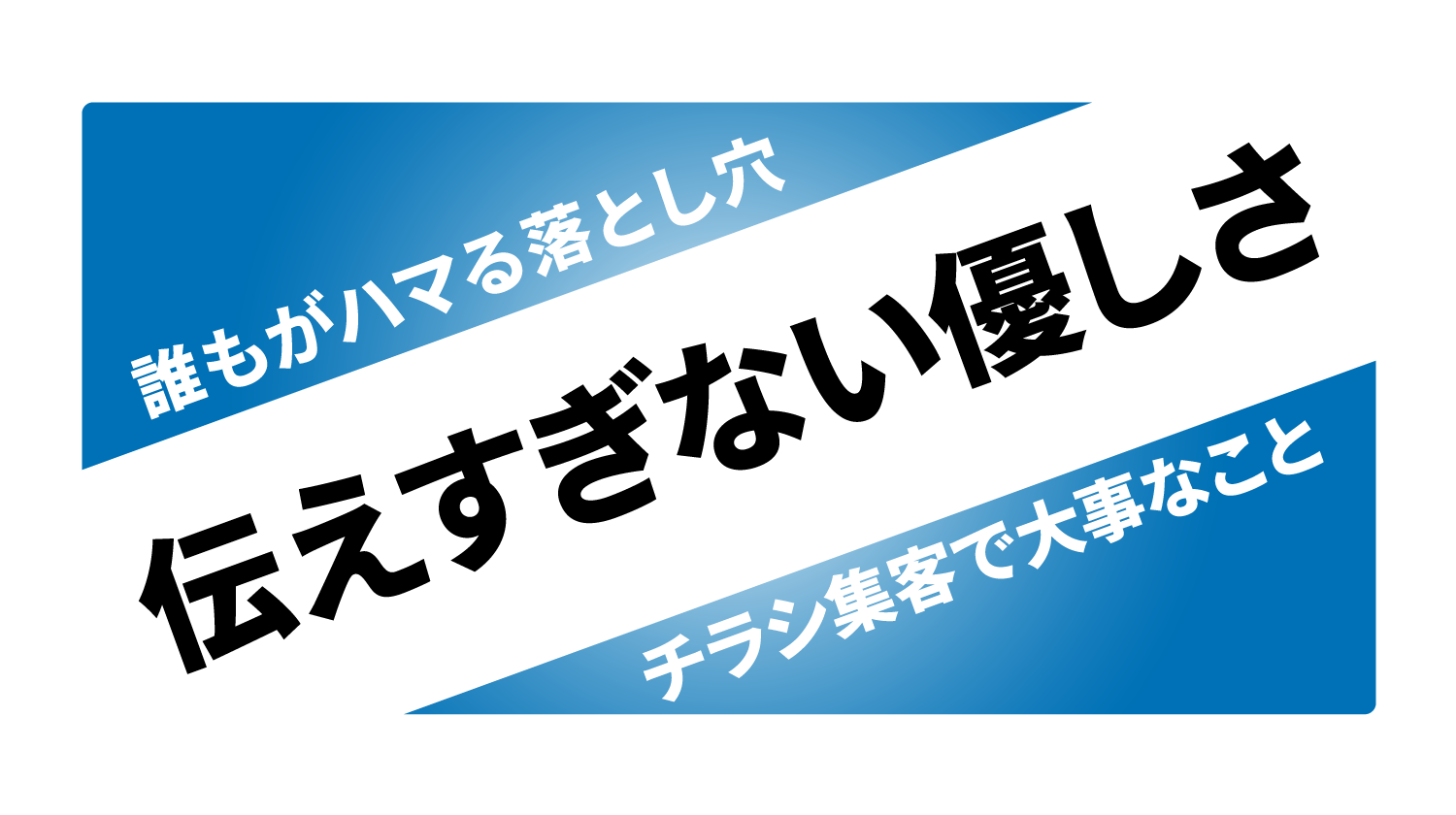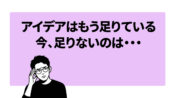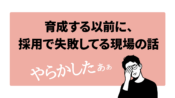【デイサービス集客】覚えてもらえないチラシは、なぜ作られてしまうのか?
「伝えすぎないこと」が読み手に対する優しさになる
こんにちは、藤見です。
最近、ある施設の方から「スタッフが丹精込めて一生懸命に作ったチラシなのに、配っても反応が薄いんです」という相談を受けました。
実際のチラシを見せてもらうと、そこにはデイサービスのサービス内容や特徴、加算や料金に関する図表、代表の言葉と紹介、外観の写真、1日の利用の流れ、年間行事やイベント情報まで、とにかく情報がぎっしりみっちり。
おそらく、
これを作っている当事者のスタッフさんは、「せっかくだから、これも載せたい」とか「少しでも魅力を伝えたい」といった思い(込み)があったんだと思います。
でも、結局のところ、それをすると落とし穴にハマってしまう。
紙面の中にあれもこれも情報が多すぎると、どれも読み手の“記憶に残らない”からです。
もっと言えば、
残念ながら、そのチラシを手に取る人の多くは、全部なんて読んでません。
チラシに必要なのは「最初の接点作り」
想いが溢れて、ついつい情報を詰め込みたくなってしまう。
これは多くのデイサービスに身に覚えがあることではないでしょうか?
「誠実に説明すれば、きっと伝わるはずだ」
「情報を省略したら、不親切なんじゃないか」
そう思ってあれもこれもしっかり書き込んでいく。
でも現実的には、文字と情報が多くなればなるほど読み飛ばされる。
最悪の場合、パッと見た瞬間にゴミ箱行きです。
介護に関心を持ってくれるかもしれなかった人でさえ、「読む気にならない」と瞬間的に判断されてしまう。
チラシの役割として大事なのは、「最初の接点作り」です。
なので、その0→1を作ろうとしている段階で“詳しい情報”は必要ないんです。
そこに必要なのは、「あっ、なんか自分もちょっと気になるかも」と思わせる“引っかかり”だけで十分。
人は「全部」ではなく「ひとつ」で動く
僕がこれまで関わってきたデイサービスや介護施設でも、
「看護師常駐」「送迎無料」「充実したレクリエーショ」「快適なお風呂」「美味しい昼食」「笑顔で明るいスタッフ」「専門的なリハビリ」など、様々な特徴がたくさん列挙されたチラシを目にすることがあります。
でも、それらすべてを詰め込んだチラシは、どれも同じように埋もれてしまって、結果的に「ふーん」で終わっていく。
その一方で、「見学いつでもOK」という一言だけ。
その単語を大きく打ち出したチラシに変えただけで、配布後の問合せが増加した、そんな例もあります。
なぜか?
それは単に、「覚えやすかったから」というシンプルなオチです。
そもそも人が記憶に残せる情報量は、思っている以上に少ないものです。
多くて2つ、だいたい1つくらいだと思っておいた方がいい。
だから、
作り手が「伝えたいこと」と、読み手が「覚えられること」の間には大きなズレがあるということを踏まえておくべきで、その点を踏まえただけでも、チラシの作り方は大きく変わってきます。
「読み手のステージ」を無視しない
僕が営業研修などの機会によくお伝えしている考え方として、「顧客心理の4段階を見極める」というものがあります。
- その1、まだ何も知らない・気付いてない段階
- その2、後回しにしている・名前を聞いたことがある段階
- その3、実際に見学に行くところを探している段階
- その4、もう余裕がない・早く見つけたい段階
下に行くほどに精神的な余裕がなくなっていくので、サービスや商品の購入ハードルは下がっていく。
顧客心理にはこうした段階がある、という話です。
あなたが地域に向けてチラシを配るとしたら、その相手は、つまりチラシを見てくれる人のほとんどは「その1」の段階の人です。
であるならば、当然その人に向けて作るべきです。
なのに、
「出会った瞬間から私達のことを全部聞いて下さい!全部きっちり説明しますから!」と書いているような暑苦しいチラシを見せられても、そりゃあ、当然うっとうしいわけです。
しかも、介護の素人には内容が難しすぎるから読んでもらえない。
もし、これが「その3」や「その4」の段階の人ならば、たとえば、利用時の細かい料金や有資格者の配置のこと、またはサービスの内容について興味が出てくるかもしれません。
でも、そうした3や4の段階にいる人の数は、「その1」に比べて圧倒的に少ないわけです。
「伝えすぎないことが読み手にとっての優しさ」
大事なことは、「すべてを伝えることが親切とは限らない」ということです。
チラシは”あなたの全部を伝える場所じゃない”です。
なので、そこで重要視すべきなのは、より詳細な情報を並べることよりも、読み手が安心して一歩前に進めるかどうかです。
たとえば、自社のサービスに興味をもってもらえるか。ホームページをクリックしてもえるかどうか。一度足を運んで見学に来てもえるかどうか。
そういったアクションに繋げるための“きっかけ”になるかどうか、を考えておくのがいいです。
事業所と見込み客(ご利用者)を繋げる橋渡し。
そのきっかけになるかどうか。
その入口が”わかりやすく”開かれていれば、チラシの反応は大きく変わると思います。
もし今チラシづくりで悩んでいる方がいたら、
一度冷静になって、「事業所の中に、何か”きっかけ”として機能することはあるかな?」と問いかけてみてください。
きっと、今まで必死に書き込んできたチラシの情報の全部は必要ないかな、と気付くと思います。
何かひとつ、で十分です。
その“ひとつ”が、チラシを手にする誰かの記憶に残れば、それはもう成功です。
それでは、また!
追伸:
メルマガ読者限定で開催している「オンライン勉強会」では、このあたりをより詳しく解説しています。
もし興味があれば、メルマガにも登録をしてみてください。
登録特典として、僕の集客セミナーの映像や1万文字以上書いたレポートも配信していますし、もう解除したくなった場合はワンクリックですぐに配信停止できます。
藤見メルマガ
特典のお知らせ

「デイサービス集客のヒントが見つかる!」と話題の”介護集客セミナー動画(90分)”をプレゼント!さらに、完全書き下ろしの”集客レポート(14,000文字)”も無料配布中です。デイサービスや介護施設の集客力アップに役立つヒントが盛りだくさんの内容です。ぜひこの機会にセミナー動画&レポートをGETしてください。